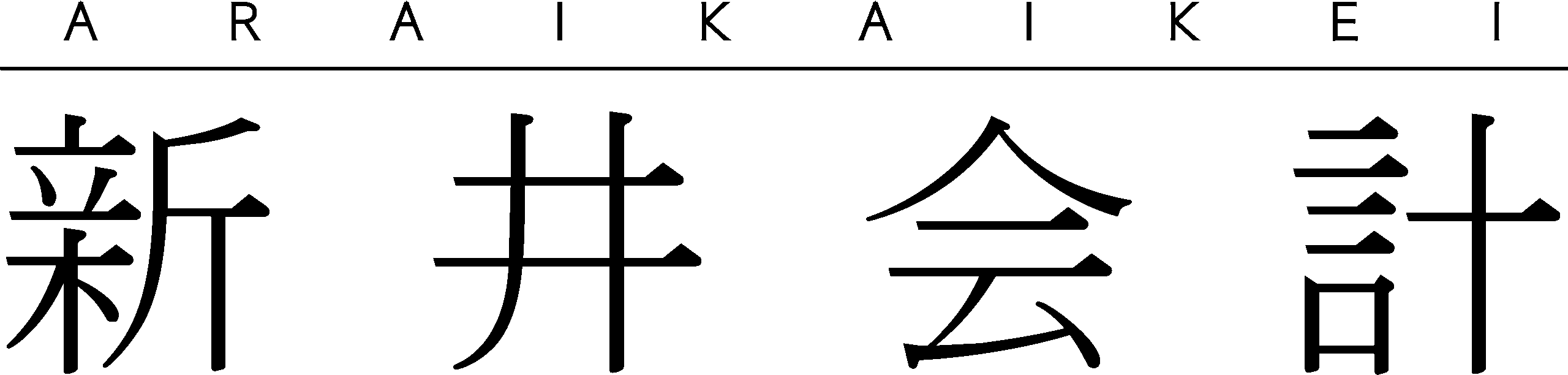公開日:2025年5月2日
減価償却の計算の特例を最大限に活用する方法
固定資産の購入費用は、通常、減価償却という方法で数年にわたって経費計上しますが、取得金額によっては特例が認められており、節税に繋がる場合があります。
減価償却の計算の特例とは?
固定資産の取得金額に応じた特例は以下の通りです。
10万円未満の固定資産
- 原則として、全額を経費として一括計上できます。
- 判定は通常取引される単位で行います
- すぐに他人に貸し付けて賃貸料を得るものは、耐用年数に応じた減価償却が必要です。
例:9万円のPCと5万円のプリンターを同時購入しても、それぞれが独立した単位とみなされ、合計14万円全額を経費にできます
10万円以上30万円未満の固定資産(少額減価償却資産の特例)
- 青色申告書を提出する個人事業主と法人(資本金1億円以下)であれば、年間合計300万円まで一括で経費計上できます。
10万円以上20万円未満の固定資産(一括償却資産の特例)
- 取得金額を3年間で均等に償却できます
- この特例には年間の適用上限金額がありません。
例:18万円のPCなら毎年6万円ずつ3年間で償却
なぜ「一括償却資産の特例」を使うのか?
10万円以上20万円未満の固定資産は「少額減価償却資産の特例」も使えますが、「一括償却資産の特例」を選択するメリットは固定資産税にあります。
固定資産税の仕組み
- 毎年1月1日時点で10万円以上の償却資産(不動産以外)を所有している場合、市町村に申告し、固定資産税(税率1.4%)を支払う義務が生じます。
- 「一括償却資産」として処理されたものは、この固定資産税の対象から除外されます。
- 「少額減価償却資産の特例」を適用した資産は、帳簿上は経費計上されていても、固定資産税の申告対象となります。
計算例:上限の300万円分を「少額減価償却資産の特例」で処理すると、年間42,000円の固定資産税がかかる計算になります。
所得税や法人税の観点では、3年間のトータルで見ればどちらの特例を使っても経費計上額は同じですが、固定資産税の負担が変わってきます。
どちらの特例を選択すべきか?
以下のポイントで判断します。
1. 利益が赤字の場合
- 減価償却期間が3年となる「一括償却資産の特例」を選択し、経費計上を遅らせるのが有利です。
2. 利益が黒字の場合
- 固定資産税の負担はそれほど大きくないため、「少額減価償却資産の特例」を選択し、早期に経費計上するのが有利です。
3. 利益が黒字で、かつ「少額減価償却資産の特例」の上限300万円を超えて固定資産を購入した場合
- ソフトウェアなどの無形固定資産は固定資産税がかからないため、これらを優先的に「少額減価償却資産の特例」で処理します。
- 残りの有形固定資産について、「一括償却資産の特例」の利用を検討します。
- 無形固定資産(ソフトウェア等)→ 少額減価償却資産の特例を優先適用
- 有形固定資産(備品等)→ 一括償却資産の特例を検討
まとめ
広島市の中小企業の皆様へ:状況に応じてこれらの特例を賢く選択することが、節税において重要です。
重要なポイント:
- 赤字企業は「一括償却資産の特例」で経費計上を遅らせる
- 黒字企業は「少額減価償却資産の特例」で早期経費計上
- 固定資産税の負担も考慮して最適な特例を選択
- 無形固定資産を優先的に少額減価償却資産の特例で処理
新井会計 新井航税理士事務所
〒730-0804 広島県広島市中区広瀬町4-22
広島市内の中小企業の経営をサポートする税理士事務所です
経営の見える化・資金調達・節税対策のご相談は新井会計へ